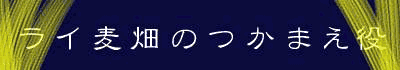
深海春樹 岬杜永司
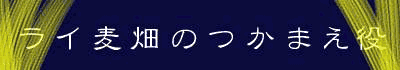
深海春樹 岬杜永司
「お前には、ほんの少しだけ不思議な力がある」
若い鷹を山に埋めに行った後、居間に行って母ちゃんに謝った。黙って聞いていた母ちゃんの顔が怖かったから、若い鷹を殺してしまった事を怒られるんだと思っていた。
それなのに、その事には一言も触れずに母ちゃんは話を始めた。
俺が小学生の頃だ。多分4年生だったと思う。
「お前は友達の目を見れば、相手が嘘を吐いているかどうか分かるだろう?」
その通りだ。上手く説明出来ないんだけれど、そうなんだ。
「分かるよ。大体は」
「お前は人に触れると、相手の感情や意思を少しだけ感じる事ができるだろう?」
「うん、本当に少しだけなら」
俺はその時、母ちゃんが大事な話をしているんだと感じた。
「お前は他人の心に触れる事ができる。そして、少しだけだが、他人が求めるモノを与える事ができる力がある。いいか、それはとても大事な力なんだ。お前の力はとても些細なモノなのだが、それでも他人には重要な力になる。これから沢山学びなさい。自分の事も、他人の事も。そして強くなりなさい」
母ちゃんの言っている事はよく分からなかった。だけれど、自分の力がとても些細なモノで、でもそれがとても重要なモノなんだって事は分かった。
俺はライ麦畑で子供達をつかまえる
深い深い崖に向かって子供達は走っていく
子供は走っている時に足元なんか見ない
だから俺は子供達が崖から落ちないように見張ってないといけない
つかまえて、抱き締めたり、髪を撫でてやったり、
足りない者には与えてやり、溢れ出る者には宥めてやる
俺はライ麦畑のつかまえ役
この高校に入ったのは俺の意思じゃなかった。別にどこでも良かったんだ。本当に。勉強はたいして好きじゃなかったし、大学行くつもりもあまりない。将来の事なんて足の小指の先程も考えてなかったいい加減な俺を、この学校に強引に入れたのは姉ちゃんだ…と思う。普段は無口な姉ちゃんが、母ちゃんに何か言ったらしい。それで全てが決定した。まぁ、よくは分からないんだけど。
一応公立の進学校を受験し見事合格したある日の朝、ぐーすかすかすか眠っていた俺は母ちゃんに叩き起こされ、試験も受けてないの県外の私立高校の入学式に無理矢理連れて行かれ……そして気付いた時には教室だった!驚きだ。だって試験受けてない。何だかわけが分からないうちに段々怒りが込み上げてきて、高校生活第一歩は最悪な気分から始まった。俺はこんな仕打ちをされた事がなかった。
俺の自慢の美人な母ちゃんと、俺より5つ上のこれまた美人の姉ちゃんは一緒に仕事をしている。家から車で30分程にあるマンションを事務所にしているんだけど、何をしているかは知らない。教えてくれない。真剣に訊いても無駄なのだ。
「私は、世界まるごとウフフン機構の一員なんだ。姉ちゃんは私の秘書さ」
とか
「私は悪の組織『ワルダーずっぽし委員会』と戦う女戦士だ。姉ちゃんと組んでる。あえて言えば私が情熱派でリーダー格、つまり子供達から愛されるレッド。姉ちゃんはクールでニヒルな、ちょっといけないお姉さん達に妖しい妄想を掻き立てられるブルーってトコかな?」
などと、全くもってぜぇーんぜん相手にしてくれない。あの二人の事だから、たいして悪い事しているわけでもないだろうと思っているけど。二人とも俺を溺愛しているのはよく分かっていたし、何か理由があるんだろうとは思う。母ちゃんも姉ちゃんも俺の良き理解者で親友で家族だ。信用はしている。
それが突然、県外の高校へ連れて行かれ、ついでに小さなアパートを与えられた。
「一人暮らししてみろ」
と、突然言われて。俺はついにブチ切れた。
「何だよそれ!母ちゃん、ちゃんと説明しろよ、俺は納得出来んぞ。大体俺が受験した高校は一体なんだったんだよぉ」
「アレは気にしなくてもいいよ。それにアンタ、『俺はどこの学校でも良いぞぉ〜』って言ってたじゃん」
「と、突然すぎてビックリするだろ!何で俺に一言もないわけぇ?」
「悪巧みが好きだから」
笑う母ちゃんに俺は言葉も無かった。
高校生活はかなり面食らう事が多かった。なんとその学校は小中高とエスカレーター式で、かなり金持ちが多かったんだ。彼等の話す事の3分の2くらいはついていけなかった。
まぁ最初は戸惑うばかりだったが、俺はどんな事もあまり気にしない性格だったし、一緒にいるのなら楽しい方がいいし、相手の良い所を見つけ出しそれを好きになるのも自然にできるから友達は増えていった。一癖も二癖もある奴もいたが、ごく普通の奴だってちゃんといる。いい奴だって沢山いた。俺は勉強はあまり出来ないが、大抵会話は楽しくできる。ついでに母ちゃんから貰った容姿のおかげで女の子からの受けも良かった。俺は皆から愛される笑顔と、図太い神経に楽天的な性格、真っ直ぐな黒髪、真っ黒な瞳、綺麗に日焼けしたすらりとした手足を遺伝してもらったのだ。
そして俺には力があった。俺の力は小さいけれど、他人に触れるだけで効果がある。友人は「深海に触ると不思議な気持ちになる」と言う。俺は「与え、宥める側」の人間だから「与えられ、宥められる側」の人間が俺に触れるとどんな気持ちになるのか分からない。落ち着く事は読み取れるけれど、詳しくは分からないんだ。でも、俺の力は好評だった。それは小さくてしかもかなり曖昧なモノなので、口では上手く説明出来ない。そうゆうモノなんだからしょうがない。だから俺は自分の力については何も言わないけれど、俺には嘘が通用しない事を仲の良い友人は知っていた。
上流階級の子供達が通うらしいその学校に、いくら私服での登校が許されているとはいえ、ジーパンとTシャツで通う俺は浮いた存在だったに違いない。しかし、俺はたいした悪意を持たれるわけでもなく、当初思っていた程辛くない、いや、辛くないどころか随分楽しい高校一年を過ごした。
そして高校2年の春、俺は岬杜永司と出会った。
クラスに入るとすぐその視線に気付いた。
強い視線。知ってる視線。
振り向くと、窓際に見たことがない男が座っていた。俺はかなりじっとその男を見ていたと思う。そいつも俺を見ていた。
身長は俺より10cm程高い。180強ってところか。髪は俺より少し長くて地毛かどうか分からないが薄茶色。俺はいかにも「得意科目は体育です!!」みたいな高校生丸出しな顔をしているけど、奴はかなり大人っぽい。本当に高校生?ってな感じ。少し目が細くていかにも冷たそうだが、全てが整っているし、身体もバランスが良い。綺麗に筋肉が付いていそうだ。雰囲気的にはかなりできる。うん、はっきり言って滅茶苦茶カッコイイぞ。俺が女だったら絶対何が何でも、どんな手段を使おうとも欲しくなる程好きになりそう。一目惚れは確実だなぁ。
そして俺がまじまじ見た最大の理由はその瞳にあった。俺は今までこんな深い瞳を持った人間を同級生の中で見たことがない。大体、大人でもそうそういないもんなんだ。母ちゃん、姉ちゃんも恐ろしい程深い瞳を持っているが、その他では母ちゃんの仕事場に遊びに行った時に時々会うお客さんの中に、こうゆう瞳を持った人が稀にいる。その程度だ。
とにかく、俺はこの深い瞳に驚いた。そして少し警戒した。深い瞳を持つ人間は、決して心を読ませない、ってか、俺には読めないから。
俺達は随分と見詰め合ったままだったと思う。
「深海君、どうしたの?」
1年からの親友岸辺和也が俺を現実に連れ戻した。岸辺は俺の力をかなり理解している数少ない友人の1人だ。俺はいい女がいないかチェックしてたぁ、とエヘエヘ笑って席についた。
イイ男は見つけたんだけどねぇ…心の中でクスクス笑いながら授業が始まるのを待っていると、同じ視線を感じもう一度窓際を見てみる。
ありゃ、やっぱまだ見てるよ。
奴は頬杖をついてじっと俺を見ていた。俺が教室に入ってからずっとだ。喧嘩売ってんのかなぁ?と思いつつもそんなふうに見えないのが不思議だったので、とりあえず俺の必殺技『85兆円の笑顔』(母ちゃん命名)をだした。
「おハロー」と心で言いながらにっこり笑ってみる。
奴は俺の笑顔を見ると一瞬凍りついたが、すぐに元に戻り何かを呟いた。勿論席の離れた俺には聞こえなかったのだが、何故かとてもドキドキしてしまった。
奴の後ろの窓から、春の空が見えた。
始業式の翌日の午後、授業をサボった俺は広い屋上で背中を柵にもたれかけて煙草を吸っていた。今日はここに誰も来ていない。
校庭の端っこには桜の木が3本あって、蕾を膨らませている。
何気なく桜を見てから柵にもたれて座り、投げ出した足をブラブラさせながらバージニアスリムの箱を弄ぶ。母ちゃんは自分が恐ろしい程のヘビースモーカーなので、俺が煙草を吸うのを見ても何も言わない。よく放任主義なのかと訊かれるが、確かにそんな感じなような、でもちょっと違うような…気がする。ぼんやり母ちゃんの事を考えていると、何かを感じ、瞬間的に顔を上げた。
そこには思った通り、奴が立っていた。
一瞬のうちに俺の身体が緊張する。こんな時は気を緩めちゃいけない、でも気取られてもいけない。黙って相手の出方を見る。しかし、俺に近付いて来た奴も黙っていた。
困った。奴の目はよく分からない。その強い視線にどんな意味があるのか、それすらも分からない。ただ俺の勘が、身体が、警戒をしている。
「名前何?」
奴が静かに口火を切った。低くて、思ったよりいい声だった。
「フカミハルキ。深い海に春の樹。樹は難しい方。同じクラスだよなぁ、宜しくぅ」
俺がごく自然に、少し微笑みながら返すと、奴も少し笑った。なんとも…なんとも言えない笑い方で。
「名前何?」
その笑い方に戸惑いながらも、それを表情に出さないで同じように訊いてみる。本当は出席をとった時にチェックしといたんだけどね。
「岬杜永司」
岬杜の強い視線を感じながらも、俺は『にかっ』と笑って見せた。岬杜がまたもや少し笑い、俺の隣に座り煙草を出す。セッタだ。
「岬杜君超カッコ良いね、マジ見惚れちゃうよぉ。髪の毛地毛?」
素直に言う俺を見て笑いながら煙草に火を点ける。その動作の1つ1つもキまっていた。
「岬杜でいいよ。…髪は地毛」
俺の身体から警戒音がする。でも、岬杜は煙草をふかしながら俺の隣でボーっとしていた。
空を見上げると、高い場所を鳶が舞っている。
何気なく話題を振ると、岬杜はぽつりぽつりと喋るだけだった。俺は身体が警戒しているのを気取られぬよう気を使い、にこやかに対応する。岬杜に悪意があるとは思えなかった。なのに警戒を続ける自分の身体に首を傾げながら、俺は綺麗に整った岬杜の顔と、強いながらもその包み込まれるような深い瞳に見惚れていた。
次の日の午後は、同じクラスの悪友と授業をサボって屋上でぼんやりしていた。真面目な岸辺はこのメンバーには含まれていない。俺様意識の強い刈田と不思議な瞳を持つ緋澄、そして俺だ。
1年の頃クラスは違えど類は友を呼ぶって奴で何故か仲良くなり、俺達はよくここで授業をフケた。2年になってこの3人が同じクラスになったと分かった時は、学校側は何を考えているのかと真剣に思ってしまったものだ。
「苅田ぁ、古典の橘ってお前好みだろぉ〜」
柵にもたれて煙草を吸いながら、俺は隣に座っていた苅田を見てからかうように言った。苅田は出会った頃から必ず俺を隣に座らせる。自分が真ん中じゃないと嫌なわけではないようで、俺が3人の真ん中に座る時もある。大抵は苅田が真ん中なのだが。
「おう、いいな橘は。あのフェロモンがたまんねぇ」
美人でムチムチした肉体を持つ古典の教師を思い出しているのか、苅田の顔がニヤつく。苅田は学生だろうが人妻だろうが中年ババァだろうが男だろうが、自分をそそるモノを持っている人間ならば誰でも抱く……らしい。口説き方もかなりシンプルで「俺に抱かれたくなったら電話して来い」と、それ専用の携帯番号を渡す。それだけ。実際俺もそう言われた。緋澄もその番号を知っているらしい。お前結局誰でもいいんじゃないのかぁ?と思ってしまいそうになるのだが、どうもそうではないらしい。奴には奴なりの基準があるのだ。
「でも実際抱く気にはなれないんだろぉ?」
「何だ分かってんじゃん」
分かってるさ。苅田は好みの女と、そそられる人間、つまりセックスの対象になる人間のタイプが違う。好みの女はムチムチフェロモンタイプ。そそられる人間は…これは俺にはよく分からんのだが、とにかく違うみたいだ。
「俺がいつも抱きたいのは深海ちゃんだけだぜ」
苅田が俺の腕を掴んで引き寄せてくる。重心が傾くと両手で俺の身体を軽く持ち上げ、あっという間に膝の上に向き合って座らせられた。
「ハッスルターイム!!」
苅田の一声で俺は途端にはしゃぎ始め、一昔前の安っぽいキャバクラ女がやるようにキャーキャー言いながら身体をくねらせる。
身長が187ある苅田の身体はしっかりと筋肉が付いていて、漲るパワーを触れるだけで感じる事ができる。喧嘩は相当強いと聞いているし、実際相当なモノだと思う。顔つきも特徴があって迫力満点。耳は勿論鼻ピアスまでしている。人を見下すニヒリストのような顔をしているが、俺はこのクセのある男が大好きだった。
少し厚めの唇と、顎を突き出し人を見下す態度は酷く魅力的で、苅田は身体中からフェロモンを撒き散らしているようだ。俺は実際淡白なのにフェロモンがあるとよく言われる。苅田からも「深海ちゃんは挑発的だ」と言われた。が、苅田のそれは普通じゃなかった。俺は苅田といるとかなり性的な気分になる。でもその高揚感は嫌いじゃない。
苅田は普段落ち着いている。無駄な揉め事は一切関知せずってポリシーがよく分かる態度を取っている。しかし、この身体は完全に実戦慣れしたモノだと俺は思っていた。俺には向けられた事はないが、苅田の瞳は恐ろしく凶暴な時がある。俺は、そんな強引で肉食獣のような瞳を奥底に持つ苅田の身体の中でじゃれるのが大好きだった。苅田にギュっと抱き締めてもらえる度に体をばたつかせ喜んでしまう。
「可愛い、深海ちゃん可愛いぜー。お前は最高だーっ」
髪にキスする苅田に身体を預けながら、俺は上機嫌だった。
「でもさぁ〜、俺の顔って絶対可愛い系じゃないと思うのよぉ。男も女も俺の事可愛いって言うけど、俺ってばカッコイイ系じゃない?」
「まぁ顔だけ見ればな。でもどんなにカッコ良くても甘え上手な猫を見れば、誰だって可愛いって言うだろさ」
「俺はネコじゃないもん」
「甘えてくるくせに懐かない、気分屋の野良猫だよ」
「の、野良猫〜?もっとカッコイイのにしてよ。例えばチィラノサウルスとかカワウソとかさぁ」
「カワウソのどこがガッコイイんだよ。それに深海ちゃんはネコ科だ」
「ええー……」
拗ねた声を出し切る前に、俺と苅田が同時に屋上の扉を見た。
「――岬杜」
強い視線を感じながら呟くと、苅田が俺を掴む腕に力を入れた。
ややあって岬杜がやって来る。昨日と同じように俺の隣に、つまり苅田の隣に座る。
「よぉ〜岬杜ぃ」
俺が苅田の背中に腕をまわしながら『ニカっ』と笑いながら言うと、奴も俺を見て困ったように笑った。微妙に苅田の身体が硬直する。
「どーもー。『深海ちゃんの世話係兼、保護者』苅田龍司、こっちは深海ちゃんの『何故だか一緒にいる係』緋澄潤。同じクラスだぜ、ヨロシク」
苅田が話しつつ俺の髪にまたキスをした。岬杜は無表情で苅田を見ていたが、黙って軽く頷いただけだった。緋澄は黙っていたので岬杜もチラッと見ただけ。
「お前いつの間に岬杜ナンパしたんだ?」
「ぶっぶぅ〜。昨日俺がナンパされたんだよぉ〜」
苅田の頬をツネてから、身体の向きを変えた。苅田の足の間に座って背中を預けると、後ろから太い腕が腰に巻きついてくる。俺が何気に煙草に火を付けると
「深海、煙草くれ」
口を開いた岬杜がそう言う。背中で苅田が驚いたのが分かった。
「メンソールだぞぉ?すっぱいぞぉ?」
「いいよ」
俺は今付けたばかりの煙草を岬杜の唇の前に持っていった。
…え?
一瞬空気が緊張した。驚いて岬杜を見ると、奴は何でもないと言うように少し笑い俺の煙草を口に挟む。でも俺は岬杜の瞳が揺れたのを見た。
「旨い」
「えへへ。だろ?軽いし、これからこれにすればぁ?」
足を伸ばしてぶらぶらさせている俺を見ながら、岬杜が包み込むような優しい顔で笑った。後ろで苅田が硬直するのと同時に
――俺はその笑顔が心に張り付いた気がした。
次もその次も、俺が授業をサボると必ず後から岬杜が顔を出した。少しずつ岬杜は俺に喋るようになり、笑うようにもなった。まぁ少し気になる笑い方だったが。
身体は相変わらず警戒するのだが俺はそんな態度を微塵も出さず、俺達は少し仲良くなった。
毎回岬杜は俺に煙草を要求し、俺も別に何でもないように煙草をやった。でも必ず箱から出した、新しい物をやった。
「深海って女いるの?」
その日も午後から屋上に上がり、二人でのんびりジジくさく日向ぼっこをしていると突然岬杜が訊いて来た。
「お?何だ突然恋の悩みか?えへへ、いやぁ、俺は決まった女はいねぇなぁ」
正直に答える。この学校の良家のお嬢様達には手は出す気になれないが、中2で童貞捨てて以来実際女に不自由した覚えはない。長く続く女もいないのだが。
「岬杜は?」
「同じ」
俺はいまだに強い視線を投げてくる岬杜を見ながら、また『にかっ』と笑った。
「今から暇?」
「う〜ん、そだね。午後からは俺のだぁい好きな体育もないし、青春のひと時を無駄に過ごすつもりだよぉ」
伸ばした足をぶらぶらさせながら答えると、岬杜は俺を真っ直ぐ見詰めてきた。
「桜、見に行こうぜ」
「あや、俺ってば桜大好きだよぉ。えへへ、桜の木に付く毛虫は怖いけどねぇ」
「行く?」
「おう!行く行くワンワン」
俺が返事をすると、岬杜はかなり嬉しそうだった。
それから俺達は学校をフケた。岬杜が場所はどこでも良いと言うので、俺のアパートの近くにある小さな公園まで俺のチャリで行った。岬杜はチャリの二人乗りなんて初めてだと笑い、俺もそんな岬杜を乗せるのが楽しかった。ステップに足を掛け、俺の肩に手を乗せる岬杜。その手のひらから感情が伝わって来そうだったので、俺は慌てて自分の力を止めた。普段は意識しなければ他人の心なんて流れてはこない。岬杜はよっぱど強い感情を持っているらしい。
公園に着くと、来る途中で買ったビールを渡しベンチに座る。小さな公園だからか俺達の他は誰もいなかった。桜はソメイヨシノをが3本と、俺の知らない種類の桜が2本。花見するには少ない本数かもしれないが、俺は桜の木が1本でもあれば充分だ。
「桜の木がドバァーってあるのもいいけど、こーゆう静かなのもいいっしょ?」
岬杜も頷いて桜を見ている。
「この桜の木、大きくて綺麗だよねぇ。俺ってば去年もここで花見したんだぜぇ」
「女と?」
「えへへ、女と花見なんかしたら気ィ使わなくちゃいけねぇからヤダよぉ。俺、花見はボケェ〜っと花見てんのがいいのよ。桜の木が『いやんっそんなに私の乱れてるトコ見ないで〜』って言うくらいね。岬杜は?」
「何が?」
「普段どんなふうに花見する?騒ぐようには見えないけどさぁ、やっぱ女と?」
「花見なんてした事なかった。今日が初めてだ」
「マジ?」
驚く俺を見て岬杜は苦笑していた。
「世界中で桜を一番愛しているのは日本人だと聞いた事がある。俺もそう思う。きっとお前も好きになるよ。毎年花見したくなるくらいね。桜って綺麗だろ?」
「ああ」
空を見上げると、春の空だった。あんまり青くない。神様が眠くて仕方なくて、寝ボケ眼で、面倒臭そうにささっと塗りましたぁ〜って感じの空。
「岬杜ってさぁ、普段何やってんの?」
「何も」
「何時も暇なん?」
「…そうだな」
嘘吐いてるな。でも、まぁいっか。
「えへへ〜、俺と一緒ぉ」
俺が笑うと、何故か岬杜まで楽しそうに笑う。
「明日も花見しよっ!」
俺が元気良くそう誘うと、岬杜は黙って頷いた。
深い瞳に俺が映っていたのが見えた。