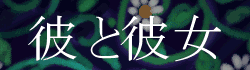
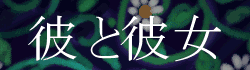
岸辺和也 深海春樹 東野奈々実
深海君を初めて見たのは、高校の入学式の時だった。僕はずっとこの学校だったから、新しく入学してきた初めて見る顔ぶれを一人一人観察していたんだ。
その中に深海君がいた。
一番格好良くて、一番目立っていて、一番気になる存在だった。
深海君は綺麗に日焼けした健康的な肌とサラサラした黒髪を持っており、少し呆然としながらパイプの椅子に座っていた。時折首を傾げながらぼんやりと来賓の話を聞いているその姿は、幼いようにも大人びているようにも見えた。
教室に入ると、深海君は僕の隣の席だった。彼は黙って担任の話を聞きながら、きょろきょろと周りを見渡したりしていた。
「ここ、どこだろ?」
彼の呟きに、僕は驚いてしまったのを覚えている。
最初、得体の知れないこの生徒は、元からいたこの私立学校の生徒達から敬遠されていた。いつも随分とラフな格好で登校して来たし、何か不思議なオーラがあるような感じがしたしで、彼は浮いていたのだ。それに彼自身、入学当初はこの学校に馴染めない感があった。
僕は彼に興味があった。いや、本当は誰もが彼に興味を持っていたのだ。彼はいつも足をブラブラさせて教室の窓から外を眺めていたけど、その姿は人を惹きつけるある種の可愛らしさがあったのだ。ただ、皆きっかけを探していたのかもしれない。彼は人見知りをするタイプには見えなかったけれど、どうしても近寄るのを躊躇わせるモノを持っていたから。
それでも僕は深海君に話し掛けてみたかった。入学式のその日に少しの勇気を持って話し掛けてみれば良かったけれども、その機を逃してしまったから、僕は何となく話し掛ける事ができなかった。それでも彼に近付きたいと思っていた。
一言、一言で良いんだ。そう思っていつも登校していた。
入学式から何日目だろうか。僕は深海君と帰る方向が同じだと気が付いた。歩いている僕を追い越して、彼は自転車に乗って帰って行った。その時、彼は僕の知らない歌を口ずさんでいた。僕は深海君にさようならを言いたかったけれど、結局何も言えなかった。
彼の背中が夕日の向こうに消えていくのが印象的だった。
入学式から二週間が経ち、登校して来た彼に僕は思い切って話し掛ける事にした。僕は昨日の夜寝る前に何度もそう決めたんだ。彼はいまだにクラスメートと馴染んでいない。この学校自体に馴染んでいない。僕はそれが気になってしょうがなかった。
自分の席に着いて彼を待っていると、妙に自分が緊張しているのが分かった。僕は友達と話をしながら、どんなふうに彼に話し掛けようかとそればかりを考えていた。教室のドアが開く音に何度も反応し、その度に心臓が大きく鳴った。
そしてHRが始まるギリギリになってやっと彼は登校して来た。僕はそれまで考えていた事なんて全部吹き飛んでしまい、友達に話し掛けられた事すら気付かずに彼を見ていた。
「おはよう」
多分僕の声はロボットのように不自然で僕の顔はお面のように固まっていたに違いない。
そんな僕を彼は驚いた様子で見ていた。その黒い瞳がきらきら光っているのを僕はドキドキしながら見ていた。
「おはよ」
返事をした彼は、そこでとびっきりの笑顔を見せてくれた。
僕の周りの生徒達が、思わず息を飲むような笑顔だった。
それから僕達はすぐに仲良くなった。彼は話してみるととても気さくで話の内容もとても面白く、僕達が仲良くなると自然に他の生徒達も彼に話し掛けるようになった。
一学期の半ばになると、彼はクラスのアイドル的存在になっていた。女の子の中にも彼のファンは沢山いた。告白されている場面も見た事がある。いまだに一度も人を好きになった事がない僕でも、彼に好意を持つ女の子達の気持ちが分かるような気がした。
誰もが深海君に少しでも近付きたがっていたんだ。
その中でも最も深海君にアプローチしていたのは、同じクラスの芳丘君だった。芳丘君はいつもヘラヘラ笑っていて、流行物が好きな感じがする生徒だった。深海君と一緒にいる時は僕にも話し掛けてくれるけれど、いない時は僕を軽蔑したような目付きで見た。
1学期が終わる寸前の土曜日にこんな事があった。
僕はその日、深海君と一緒に昼食をどこかへ食べに行く約束をしていた。授業が終わって教科書を鞄の中に入れていると、芳丘君が来て深海君をどこかに誘った。僕の知らない場所だったから、それが何なのかどこなのか分からない。深海君はすぐに僕との約束があると断ってくれたが、それでも芳丘君はしつこく深海君を誘っていた。
「芳丘も一緒に昼飯食いに行こうよぉ」
深海君の言葉に芳丘君は固まっていたが、僕だって硬直した。
僕は芳丘君が苦手だったからだ。
「岸辺ってさ、地味だからな」
芳丘君の呟きに、心がチクリと痛んだ。彼は、いつも地味な服を着て厚いメガネをかけているダサイ僕と歩くのが嫌なんだ。
「んだよそれぇ」
深海君が不機嫌そうに言う。
「だってよ、コイツ鞄に教科書パンパンに入れてんじゃん。今時サラリーマンだってそんなデカイ鞄持ってねーよ?それにコイツの…」
「――岸辺は俺の友達。岸辺の悪口は俺の悪口」
深海君は芳丘君の鼻を摘んでピシャリと彼の言葉を止めた。それから芳丘君が何を言っても深海君は相手にしなかった。僕は深海君に引き摺られるようにして教室を後にしたけれど、彼は何事もなかったように僕に話し掛けてくれた。
僕はそれでも芳丘君との事が気になって、昼食を食べながら彼に尋ねみた。
「どうして深海君は僕と一緒にいるの?」
彼は少し驚いたように僕を見た。
「一緒にいるのに理由いるのか?」
理由はいるのだろうか。分からない。でも深海君はどうして僕の側にいてくれるのだろう。僕はあまり格好良くない。
僕が黙ると彼は優しく微笑んだ。
「岸辺といるとほっとすんだぁ」
僕は芳丘君の事など全部忘れて、彼の笑顔と言葉に感動した。
月曜日に芳丘君は深海君の前で僕に謝ってくれたけれど、それは本心じゃないと思う。芳丘君はただ深海君と仲良くなりたかったんだ。それだけだったんだと思う。深海君もそれは分かっていたみたいだけど、芳丘君を嫌う事もしなかった。誘われて、その日に予定がなければ一緒に遊びに行っていたみたいだった。僕もそれは気にならなかった。芳丘君は苦手だけれど、それでも芳丘君だって深海君の友人の一人なんだと分かっていたからだ。
深海君は誰からも愛された。
それが当たり前のように誰からも愛されていた。
特権階級の意識が強い生徒からも、別にペット扱いされるわけでもなく同じ男として、同じ生徒として、同じ人間として愛されていた。
彼はそんな魅力を持っていたのだ。
それでも、深海君の一番の友達は僕だった。深海君は僕に色々と話をしてくれた。家族構成や幼い頃の話や引越しが多かった事、そして入学試験を受けていない事などを。僕は彼と親友になった。それは僕にとってとても素敵な事だった。
僕は何の取り得もない凡人だけれど、彼は僕と一緒にいた。僕はいつも彼の話を聞いて笑っているだけだし、彼のように話題豊富なわけでもないつまらない人間なのに、彼は僕の側にいた。
夏休みに僕が家族と一緒にロンドンに旅行に行った時も、ちゃんと手紙をくれた。エアメールを送るのは初めてだからちゃんと届くか心配だとか、自分は毎日バイトをしているとか、最近日本ではこんな事件があったとか、夏休みの課題を全然やってないとか。お盆に入ると、今は実家にいるから母親が五月蝿いとか、今日はナツアカネを追いかけたとか、夜にはクワガタ獲りに行く予定だとかって感じに内容が変わった。
何気ない内容だったけれど、深海君は長い手紙を書いてくれた。何通もくれた。
僕はこの手紙を今でも持っている。
きっと、一生持っているだろう。
深海君に不思議な能力があると気が付いたのは、この学校では僕が最初だろうと思う。
彼の手はとても特殊な感じがする手だったのだ。敢えて言葉にするのは非常に困難だけれど、例えば森の中にある湧き水や、春の暖かな日差しや、朝の光、砂漠の中のオアシス、マラソンランナーが必死で手を伸ばす清涼飲料水、それらのモノを全て含んだ手だった。僕は何も言わなかったけれど、彼に触れてもらうと心が落ち着いた。僕の中に、彼が直に生命の息吹を吹き込んでくれるようだった。
初めて深海君の口からその力の話を聞いたのは、2学期の初め、
僕達が一緒に下校していた時だ。
その日僕は深海君の部屋に遊びに行く予定で、彼の自転車のステップに乗せてもらっていた。
彼のアパートの近くに小さな公園があって、そこに小学生が集まって遊んでいた。僕が深海君と話をしながらその公園を見ていると、急に彼は自転車を止めて暫く何かを見ていた。何だろうと思っていると、彼は僕を自転車から降ろし、公園内に入って行く。
「ここで待ってて〜」
深海君は僕にそう言うと、子供達の方へ向かって歩きだした。僕がそこで見ていると、深海君は子供達の輪の中に入り、その中心にあったモノを抱き上げた。
足に怪我をした仔犬だった。
僕は彼の元に走り寄ると、深海君は子供達にこの仔犬の事を訊いている最中だった。
この仔犬は誰のものか。
この仔犬の怪我は誰が負わせたものなのか。
この仔犬をどうするつもりなのか。
子供達は口々に「知らない」「分からない」を連発していた。深海君もあまりしつこくは追求せず、最後に
「この仔犬をいじめちゃ駄目だよ」
とだけ言い残し、僕と一緒に公園を後にした。
「嘘吐いてる」
深海君の小さな呟きが聞こえた。
その時の僕には、何の事なのかは分からなかった。
それから自転車に僕を乗せ、少しだけ移動し、また止まる。どうしたのか訊いても深海君は返事をしない。僕は不思議に思いながらもう一度訊いてみた。
「どうしたの?」
深海君はポケットから煙草を出し、火を点けた。
「あの子達、嘘吐いてる」
深海君はそれ以上何も言わなかった。
それから僕は、深海君のもう1つの能力を知る事になった。
公園の方から仔犬の鳴き声が聞こえたのだ。それは明らかに悲鳴だった。
子供達があの仔犬に何をしたのかは分からないが、とにかく深海君は走って公園に入って行き、僕が追いついた時には腕に仔犬を抱えて子供達を諭していた。諭していた、というのは語弊があるかもしれない。深海君は何も言っていなかったし、何もしていなかったのだから。
ただ子供達の手を取り、黙っていた。
でも、僕にはそれが諭しているように見えた。
それから深海君は子供達の手を放し、仔犬を抱いたまま公園を後にした。
「岸辺の家はさぁ、ワンコ駄目?」
「駄目なんだ。母が動物アレルギーで」
深海君はキュンキュン鳴く仔犬を抱きながら片手で自転車を引っ張って歩いていた。
仔犬の足は何をどうしてこんな事になったのか引きちぎられたようになっていて、傷口からは肉が見えていた。
「俺のアパートも駄目なんだぁ。どーしよ…」
深海君は暫くとぼとぼと歩き、ふと携帯を取り出した。
「やほ〜。深海だけど」
誰かと話している。
「犬欲しくない?犬だよ犬。コ・イ・ヌ。え?俺じゃないってば!ワンコ!」
深海君は誰かと話しながら自分のアパートを通り過ぎてしまっていた。僕はどうしようと思いながらも、それでも深海君に付いて行く。
「ホント?絶対ホント?んじゃ、俺ン家の近くまで来たら携帯鳴らして。待ってるよん」
話が終わると立ち止まる。そして僕に仔犬を預け近くのATMに入り、すぐ出てきて今度は動物病院に向かった。
僕はただ深海君の後を付いて行くだけだった。
ふと、自分1人だったら何をしただろうと思う。
まずあの子供達が何をしているのか気が付かなかっただろう。いや、深海君より随分と高い視点から見ていたのに気が付かなかった。
それにいまだに彼等がこの仔犬に何をしたのか良く分からない。
そして、もし気が付いたとしても僕はここまでしない。
子供達に一応注意はする。しかし、もしあの子供達が中学生だったらしないかもしれないし、高校生だったら見ていない振りをするだろう。仔犬を助けたとしても、僕ならその場でさよならをする。誰かに連絡してまで飼い主を探してあげようとは思わないし、そんなに友達もいない。それに、動物病院にも連れて行かないかもしれない。
僕は冷たいだろうか。
深海君が優しいのだろうか。
「深海君は、捨て犬を見つける度にこうして世話をしているの?」
「まさか〜」
動物病院の待合室は、人と動物で一杯だった。
「どうしてこの仔犬は助けたの?」
「別に理由はないよ。ただこのままだと保健所に連れて行かれるだけだろうし、足の怪我は人間がやったモノに見えたし、たまたま友達に犬好きがいたのを思い出しただけだし、そんでもってそいつが引き取ってくれるらしいし。そんな感じなのぉ」
深海君は仔犬を抱きながら、足をブラブラさせて他の動物を見ていた。確かに深海君は特に動物好きなわけではなさそうだった。腕に抱いている仔犬もずっと抱いてはいるのだが、だからといって甘やかすわけでもなく、ごくごく普通に抱いているだけだった。
そのうち深海君の順番が来て、診察室に入っていく。僕はそのまま待合室で待っていた。
深海君は気まぐれで仔犬を助けた。
それは本当に気まぐれなのかどうなのか、僕には分からないけれど。
でも、僕は仔犬も仔猫も助けた事はない。家に持って帰っても母はアレルギーだし、捨て猫を見てもいつも「誰かが拾ってくれるだろう」と思う。
診察室から出てきた包帯をした仔犬と深海君は、料金を払って動物病院を後にした。
深海君の少し後ろを歩きながら、僕は彼の後ろ姿に見惚れていた。彼と出会ってからいつも感じていた事だが、彼は僕の知らない生き物のようだ。
夕日が長い影を作り、僕のと彼のが重なる。
「ねぇ深海君。捨て猫を見ても、誰かが拾ってくれるだろうって思ってそのまま通りすがった事はある?」
僕は無意識に、自分の影が深海君の影から出ないように気を使って歩いていた。
「あるよ。そんなんしょっちゅう」
深海君は普通に答えてくれた。僕は何故か彼の答えにとても安堵していた。
深海君の家の前には同じ学校の苅田君が待っていた。
彼はこの学校で一番の有名人だった。バイセクシャルで喧嘩がとても強く、そして高校一年生とは思えない程の大人びた身体付きと雰囲気。威圧感と存在感。良い噂はあまり聞かない。
深海君は今まで他県で暮らしていたし今だって違うクラスなのに、どうして苅田君と知り合いなんだろうと不思議に思った。
「ありゃ、いつ来た?」
「今携帯鳴らそうと思ってたトコ」
僕は苅田君とは話した事がない。正直に言うと彼はちょっと…いや、凄く怖かった。
「コイツ雑種だけど大丈夫?」
「大丈夫。深海ちゃんが名前付けてくれ」
「俺が?イヤだなぁ」
「いいから」
「んじゃ、ワンコ」
「んだよそれ。そのままじゃん」
苅田君は笑いながら深海君の髪を撫でていた。まるで女性を口説いているようないやらしい感じがしたけど、僕は後ろでじっとそれを見ているだけだった。
「だって決めらんないもん。ホントに何でもいいの?」
「いいぜ」
「ん〜。……バンさん」
「バンサン?」
「違うの。バン。バンさん」
「何でバンなんだ?」
「さっき動物病院の先生に傷見てもらった時、バン!って鳴いたからぁ」
苅田君は笑っていた。仔犬の名前はバンに決定し、苅田君は後ろに待たせていた車に乗り込んで帰って行った。苅田君は一度も僕を見なかった。彼はずっと深海君を見ていて、深海君の髪を撫でていた。
僕はそれを見ているだけだった。
それから深海君は満足そうに微笑んで、僕をアパートに入れてくれた。
深海君の部屋に入ると僕はとても嬉しくなる。そこには僕が今まで見た事もなかったような物が乱雑に積み重ねられており、僕はそれらを手に取って眺めたりするのが楽しかった。深海君に関する全てが、僕にとって新鮮だったのかもしれない。
「そういえば、どうして子供達が嘘を吐いてるって分かったの?」
僕はラックに入ったCDを眺めながら訊いてみる。
「何となくだよぉ」
深海君が台所から飲み物を持って来てくれた。
僕はそれを受け取り、もう一度訊いてみる。
「どうして分かったの?」
深海君が僕を見た。
「何となくだってば。俺は勘が良いの」
僕は深海君の目を見ながら、苅田君の事を考えていた。彼は深海君についてどこまで知っているのだろうか。どこで知り合って、どのくらいの仲なのだろうか。僕よりも仲が良いのだろうか。深海君の不思議な力をどこまで知っているのだろうか。
僕は苅田君がしたように、深海君の髪をそっと触ってみた。それは僕が思っていたよりずっと綺麗でしなやかな感じがした。そしていつまでも彼の髪を撫でていたくなるような、そんな気分になった。
「どうして分かったの?」
僕は引かなかった。彼の一番の友達は僕。
僕は深海君の手を握ってもう一度訊いた。
「どうして分かったの?この手には何があるの?」
深海君は暫く黙って僕を見ていた。
僕は彼を知りたかった。深海君を誰よりも知っていたかった。
それから深海君は自分の力について説明してくれた。「自分でも上手く言えないんだ」と言いながら、それでも僕には話してくれた。他人の嘘が分かる事。他人の感情を少しだけ読める事。人がいてはいけない場所が分かる事。そして他人が求めるものを与えることができると。
「俺の事、気持ち悪いとか頭オカシイとか思う?」
深海君は話をしながら度々僕に訊いてきた。僕は笑いながら否定した。人は他人に知られたくないものを持っている。それを勝手に探られるのは確かに不愉快だろうが、深海君の力はそこまではっきりとしたものではないらしい。もっと漠然としていて、もっと大きなものだと思った。深海君の能力は話だけ聞けば到底信じられるものではなかっただろう。
でも僕は実際深海君の力を知っている。
僕は深海君の話を聞きながら、その力に関する驚きや慄きよりも、深海君が僕にこの話をしてくれた事に感動していた。
深海君は僕達普通の人間とは違う世界で生まれ、違う空気を吸って生きて来た。
そしてその深海君の理解者は、僕なのだ。